山下達郎さんが2023年5月4日放送のNHK FM『今日は一日“山下達郎”三昧 レコード特集2023』の中でレコード・カセットが再販売されることになったRCA/AIR時代の8作品についてトーク。『SPACY』について話していました。
(杉浦友紀)さあそして、続いて参りましょう。1977年リリースの『SPACY』です。初期作品では、このアルバムのファンがとっても多いですよね。
(山下達郎)そうですね。非常に内向的なアルバムですからね。
(杉浦友紀)このアルバムでは国内最高峰のミュージシャンたちとのレコーディングが。
(山下達郎)これも妄想でね(笑)。これのために組んだ村上秀一さんと細野晴臣さんと松木恒秀さんと佐藤博さんっていうのがこれ、組んだらどうなるかな?っていう。初顔合わせなんですよ。
(杉浦友紀)ああ、その場が?
(山下達郎)その場がね。だから逆にそれが緊張感を生んで、いい演奏になってるんですけど。
(杉浦友紀)達郎さん、前回ライブの時も、その「緊張感がいいものを生む」っていうお話をされていたんですけど。レコーディングでもそうなんですか?
(山下達郎)もちろんそうです。だからやっぱりそれは曲の難易度とか。ストリングスでもやっぱりずっと、白玉っていって。全音符をずっと弾き続けると結局、言っちゃ悪いけど手抜きになるんですよね。飽きちゃって。だからそれを、やっぱりきりきり舞いさせるようなのだと、真面目にやるでしょう? それが、演奏可能か不可能かは別として、そういうある程度の難易度っていうのをちゃんと出さないと、演奏はダレますから。
それは作曲家とか作詞家とか、歌手に歌ってもらうっていう、たとえば作曲家みたいな人も、そういうものをやっぱりある程度、難易度をつけて。だからアメリカのスタンダード……20年代、30年代、40年代のあの頃のアメリカのスタンダードっていうのは、完全な分業制なんで。作曲家、作詞家と歌手ってのは全部別の職制なんですよね。アレンジャーの違うでしょう? すると、作曲家っていうのはね、僕はいつも言うんですけど。作曲家の定義って、自分が歌えない曲を書ける人なんですよ。
(杉浦友紀)ほー!
(山下達郎)で、歌手に「こういう曲を歌えるか?」って、提示するわけですよ。だからアメリカのスタンダードって変な転調が多くて、難しいんですよ。それを歌手が何の苦もなく歌える。「どうだ?」ってね。そうすると、作曲家は「じゃあ、これはどうだ?」っていう。そういう丁々発止があるから、曲も歌唱もどんどん伸びていくっていう。だからアスリートと同じですよね。そういうことが僕が「緊張感」って言っている意味なんですけどもね。
(杉浦友紀)挑戦、チャレンジという。
(山下達郎)だから自分が曲を書いたら、それをミュージシャンに演奏してもらうんだけど。それが、たとえばノウハウというか。ドラムがどういうことができるかとか……だから要するに編曲法ですよね。そういうものがある程度、知識がないと。「こういう曲なんだけど、これ、やってみて」って。だけど、ミュージシャンの方にそういう自意識がちゃんとあればいいですけど、「そんなの面倒くさいな」と思ったりね。そういうのが、いろいろあるわけですよ。そういうところのコミュニケーションの密度のあり方っていうか。そういうのを考えるのがプロデューサーの仕事で。
それで、プロデューサーがそういうことを考えて、作曲家と、編曲家と、それから演奏家と、それを歌う人間と。それから録音するエンジニアも。ある意味での総力戦としての緊張感みたいなもの。それがいいテイクを録れるかどうか、いいレコードが残っていくか。あとはそれがやっぱり20年、30年経っても鑑賞に耐えうるか。耐性ですよね。耐久力。そういうようなものになっていくっていうか。それの結果なんですよ。まあ、後だから言えるんですけども。こんなものは。やってる時は必死ですからね。
(杉浦友紀)でも『SPACY』では、それこそいろんなことにトライしたっていうお話で。
(山下達郎)そうですね。ただ、売り上げ的に空回りしてるっていう(笑)。
(杉浦友紀)でも本当に予算がない中、いろんな試みをしたと達郎さん自身もおっしゃってますもんね。どんな試みだったんですか?
(山下達郎)スタジオミュージシャンって、高いんですよ。1時間で8000円、取るんでね。そうすると、カウベルひとつ叩くんでも8000円、取られるんですよ。それだったら、自分でやった方がいいやっつって。そういう、自分でできるところはなるべく自分でやるようにしてきた歴史なんです。『GO AHEAD!』までは。
(杉浦友紀)ええ、ええ。
(山下達郎)そうすると、自分でギターソロを弾くようになるし。で、パーカッションは元々僕、ドラマーだったんで。ブラバンでパーカッションだったんで。パーカッションはだから少しずつ、自分でやるようになって。それで、そうすると今、ジュラルミンのケースが三つになってますけどもね。パーカッションが入っている。それで今でも、スタジオでミックスする時に「ここに何か入れたい」っていう時に、人を呼ばなくても済むわけですよ。だから言ってみれば、ヒップホップだとかの自分で自宅で全部、シンセを使って音楽を作ってる人と同じような発想なんですよね。1人でできることは全部、1人でやろうっていう。
(杉浦友紀)できないことをじゃあ、プロフェッショナルに任せるっていう?
(山下達郎)そうです。まあ、たとえばバンドとか、こういうスタジオミュージックでもそうですけど。5人なら5人で集まった時に、やっぱり5人が10人分ぐらいのグルーヴを生むっていうものがあるんですよね。それは1人じゃできないんですけど。そのバランスというかね。それが、難しいですよね。だから1人で全部構築するっていうことをすごく……だから僕、多重録音が好きなのは、そうするとたとえば目立たなくていい音でも、隠し味でも別に不満じゃないですけど。スタジオミュージシャンってやっぱり自分の音を聞きたいんですよね。そういうようなところだと、やっぱり積みっつって。
キーボードのポジションで弾くとか、ギターのどのポジションで弾くとか、目立ちたがるっていうか。でも、それがアンサンブルを崩す場合もあって。1人で全部やると、そういうことがなくて、まとまったオケにはなるんだけども、それ以上のものにはならないっていう。だから、始めたらキリがない。いいところで……屏風みたいなもんで。両端を広げすぎると、前後に倒れるし、すぼめすぎると左右に倒れるっていう。そのいいところの広げ方。そういうものがないとダメなんだっていう(笑)。
(杉浦友紀)そうなんですね。で、この『SPACY』からは2曲、お聞きいただきますが。まず選んだのが『素敵な午後は』です。
(山下達郎)渋いところですね。
(杉浦友紀)はい。渋いのを選ばせていただきました。この曲を聞きながら、ゆるっとコーヒーでも飲む午後があったら幸せだなと思うような曲ですけれども。バンドのアドリブが炸裂したレコーディングだったという話ですけども。
(山下達郎)スコアを書いて……だから『CIRCUS TOWN』でいろいろ学習してスコアを書いたんだけども、なんにも言うこと聞いてくれないんですよ(笑)。
(杉浦友紀)言うことを聞いてくれない?
(山下達郎)言うことを聞いてくれない。まあ、でも一流の人はそれでもいいんですよね。
(杉浦友紀)でも、かえって良くなったってことですか?
(山下達郎)だから自由度と、要するにたとえばスコアという名前の束縛と、どういう塩梅でやるか? だから、さっきと同じです。問題は。塩梅なんですよ。全部。でも、うまい人だったらそこの先を見るので。なんというか、アレンジャーの発想だけじゃないことが出てくるっていうか。そういうファクターもあるのでね。そこをうまく引き出せるかどうか。それはでも、作品とかそういうものの力も必要だし。なかなか難しい(笑)。
(杉浦友紀)でも、このメンバーだったからできた曲ですよね?
(山下達郎)そうですね。この頃シカゴのリズム&ドブルースに耽溺してたので。そういうような、シカゴの感じっていうか。そういうものは、よく出てますね。このメンバーの演奏だとね。
(杉浦友紀)では聞いていただきましょう。『素敵な午後は』。
山下達郎『素敵な午後は』
(杉浦友紀)うわー、右から左から、とってもきれいなギターの音が聞こえてくるという。
(山下達郎)右は松木恒秀さんで、左は大村憲司さんですね。
(杉浦友紀)さあ、そして続いて、この『SPACY』から選んだのは『DANCER』です。
(山下達郎)渋いですね(笑)。
(杉浦友紀)いやー、これはだってもう、あのですね、イントロのポンタさんのドラムが……。
(山下達郎)これはだから、ポンタが演奏するんだったらこういう曲だと思って作った曲なので。結局、いつも言ってますけど。メンバーがこういう人だったら、どんな曲がいいかな?っていう。僕、座付きなんですよ。変な言い方ですけど。近松門左衛門みたいなもんで。座付き作家っていうか。そういうのが得意なんですよ。
(杉浦友紀)実際にそのポンタさんにこの曲を渡した時に、どんな反応だったんですか?
(山下達郎)まあ、でもあの頃はみんな、1日3セッションぐらいの人たちですからね。いちいち覚えてないですよ。で、結局やっぱり10年、20年と経つと記憶に残っていくんですよね。で、やっぱり細野さんとポンタのセッションで、本当にこれが2日目ぐらいですけど。
(杉浦友紀)2日目!
(山下達郎)初日が『LOVE SPACE』ともう1曲、なんかをやって。これが2日なんですよね。
(杉浦友紀)たったの2日でこのグループが出るんですか?(笑)。
(山下達郎)いや、だからそれはこっちが計算するんです。
(杉浦友紀)計算ですか?
(山下達郎)そうです。だからポンタと細野さんだったら、こういう曲がいいんじゃないか。それで、松木さんが途中でギターのリフをやったりする。この『DANCER』はキーボードいなかったんで、自分で弾いてるんですけどね。で、途中のピアノの速いやつは坂本くんに頼んでるんです。そういう……この曲はね、不思議なことにとにかく2000年代に入ってから、やたらと欧米でね、サンプリングされるんですよね。わけがわかんないんです。

(杉浦友紀)これ実際、今の新曲だって言われても信じるし。逆にもうこんな曲は今じゃ生み出せないんじゃないかって思うような、不思議な曲だなって私も思っていて。
(山下達郎)僕の高校の1年先輩がいましてね。在日コリアンの人だったんですけど。万景峰号で北朝鮮に帰ったんですよ。本当に頭のいい人で。それで僕は上野まで彼を送りに行ったんだけど。「俺はこれから王道楽土へ帰るんだ」っつってね。その彼のことを歌った歌なんですけど。だから非常に抽象的な内容ですけど。その彼の感じの記憶で作った曲なんで。それがまあ今、どうしてるか全然わからないけど。もう、それこそ50年前の話ですからね。
(杉浦友紀)私は2分25秒ぐらいから始まる間奏の部分が大好きで。もう本当にいろんな音が、みんながみんな投げ出すというか、飛び込ませるといいますか。なんていうんだろうな? もう、それを聞くとニヤニヤしちゃうんですよね。
(山下達郎)もうとにかくパターンミュージック、同じビートがずっと続く曲っていうのはこの頃は、要するに「手抜きだ」と言われたんですよね。でも、ダンスミュージックっていうのは基本的にそうやって継続しないとダメなんですけど。そういうことはあんまり理解してもらえない時代だったんで。「変化、変化、変化」っていうかね。たとえば変な話だけども、『RIDE ON TIME』って「青い♪」って歌から始まるでしょう? あれは「手抜きだ」って言われてね。「イントロがない曲は手抜きだ」って。
(杉浦友紀)へー! そうですか。
(山下達郎)信じられないでしょう? だから、そういう時代だったんですよ。
(杉浦友紀)そういう時代なんだ。では、聞いていただきましょう。『DANCER』。
山下達郎『DANCER』
(杉浦友紀)お聞きいただきましたのは『DANCER』でした。リズムの中にちょっとした変化がありますね。
(山下達郎)変化がね。小さな、要するにバリエーションというかね。パターンミュージックの中に、そうやって……そこで主張するんですよ。それが渋いんです。
(杉浦友紀)それがその、一流のベーシストだったり、一流のドラマーだったり?
(山下達郎)完全なフリーじゃないんですけど。モダンジャズみたいな、そういう完全なフリーとは違うんですけど。だけど、このいわゆるパターンというかね。パターンというのは基本的にイコールダンスミュージックのためのものなので。だけど、その中に自分のちょっとした変化を差し入れていくっていう、そこのセンスですね。
(杉浦友紀)いやー、センスの塊みたいな曲だなって。
(山下達郎)でもね、とにかく予算がないんで、時間がないでしょう? 歌入れがもうとにかく、必ず最終的には歌入れにしわ寄せがくるんですよ。だから歌を入れるのが朝の4時とか。
(杉浦友紀)朝の4時!
(山下達郎)これは、アルバム半分はもう11時から朝の4時ぐらいまでで3曲、4曲やって。だからもう『GO AHEAD!』とか、そういうところまでだいたいシングル盤はみんなそうですよね。『さよなら夏の日』も朝の4時だし。
(杉浦友紀)へー! 声を作るの、大変ですね。
(山下達郎)だって、しょうがないですね。それで発売日が遅れたりするから。
(杉浦友紀)そうか。さあ、ここまでは『SPACY』についてお話を伺いました。続いては、1978年リリースのライブアルバム『IT’S A POPPIN’ TIME』。初期作品の中でももう……(笑)。珠玉のライブアルバムですね。
<書き起こしおわり>

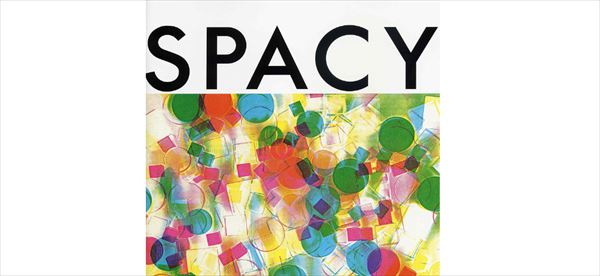
![【Amazon.co.jp限定】SPACY (完全生産限定盤) (アナログ) - 山下達郎 (ジャケット絵柄メガジャケ付) [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/51NS7nvtnCL._SL160_.jpg)