(宇多丸)ということで、1980年代半ば。まあいままでは演奏をし直したり。あと、ドラムマシーンを中心としたビートっていう感じだったんですけど、サンプリングマシーンを……昔からサンプリングマシーンはありましたけど、たとえば「ギャンギャン」とか「ワンワン」みたいな、アート・オブ・ノイズみたいなああいう使い方がサンプリングは結構あれだったんだけど。
曲の一部を丸ごと使ってループを……要するに、ターンテーブルのレコード2枚使いを曲の中で再現するというか。そういうい手法が1980年代半ばに出来上がる。これを主に進めたのがマーリー・マールさんという方ともう1人、セッド・ジーさん。ウルトラ・マグネティック・MC’sというグループの方がいて。狭い地域の話ですから。この人たちが結構さ、セッド・ジーの使っていた機材をみんな使いまわしてやっていたりとかね。
(高橋芳朗)そうね。それこそ、(サンプラー)SP1200とかはブロンクスで1人しか持っていないとか、そういう感じですね
(宇多丸)みんなそこに行ってサンプリングしてもらうみたいな、そういう時代なんですけども。みなさん、いままで聞いてきたビースティ・ボーイズとかLLとかラン・DMCとかとはガラッとサウンドの感じが変わるのをちょっと楽しんでいただきたい。マーリー・マール。コールド・チリンというレーベルで大活躍していましたが、1987年のこの曲をまず代表曲として選んでみました。ビッグ・ダディ・ケインで『Raw』!
Big Daddy Kane『Raw』
(宇多丸)はい。ということで、ビッグ・ダディ・ケインという非常に色男ラッパーにしてラップがめちゃくちゃ上手いラッパーの『Raw』という1987年の曲。マーリー・マールの作るサウンドの代表作として聞いていただきました。ビッグ・ダディ・ケインは後にマドンナのヌード写真集。あれにも出たりとかっていうのもありましたけども。どうですか? いままでずっと聞いてきて、割とエッジが立ったサウンドが多かったところに、ちょっとスモーキーなというか、サンプリングのちょっと音が悪い感じ。この時代に音が悪い感じがかっこいいというのがあったわけですね。だいぶ時代が変わってまいりました。
同じように、同時代のを聞きましょうか。先ほど、ちょろっと名前が出ましたね。ウルトラ・マグネティック・MC’sというグループ。この中のセッド・ジーという音を作っている人が……まあ、ラップもやるんですけど。彼の作るサウンドの影響がすごく大きかったという風に言われていますよね。まあ、後のパブリック・エナミーのサウンドとかも、セッド・ジーの影響が強いとか。あと、先ほども言いましたけど、要するにサンプラーをブロンクスで唯一持っていたという。SP1200という名機。
(宇多丸)非常にいい音がするというか、荒っぽい音がするんですね。SP1200という名機を持っていたということで、後にもかけますけども、ブギーダウン・プロダクションズのアルバム製作にも関わっているという、非常に……。
(DJ YANATAKE)日本だとデブ・ラージさんがね、すっごい影響を受けてますね。
(宇多丸)ウルトラ・マグネティック・MC’s。まさに後ほど……この後どのぐらいかな? かかると思いますが、ブッダ・ブランドというグループのサウンド感であるとか。あと、世界観とかもね、影響を受けているかもしれませんね。ということで、ウルトラ・マグネティック・MC’s。これ、でも1986年。早いんですよね。ウルトラ・マグネティック・MC’sで『Ego Trippin』。
Ultramagnetic Mc’s『Ego Trippin』
(宇多丸)はい。ウルトラ・マグネティック・MC’sで『Ego Trippin』。1986年でこの感じ、早いですけどね。ウルトラはちょっとアルバムを出すのが遅かったんで。
(高橋芳朗)「キング・オブ・シングルス」なんて言われていましたね。
(宇多丸)これね、セッド・ジーともう1人ラッパーのクール・キースという人がいて。この人が非常にぶっ飛んだ……。
(高橋芳朗)まさにデブ・ラージさんが大好きな。
(宇多丸)歌詞の内容で。いままでの割りと日常的な「俺自慢」的なところから離れて、宇宙的な規模のぶっ飛んだ比喩とかね、そういう感じが使われるようになった。ということで、結構ラップのもちろん聞こえ、フロウの技術もそうですけど、中身とか詩的な表現としてもだいぶ進化したのがこの時代っていうことですよね。
(DJ YANATAKE)あと、この2曲。『Ego Trippin』の冒頭とか、さっきのビッグ・ダディ・ケインとかもスクラッチも結構、すごいかっこいいものになってきていましたね。
(宇多丸)ああ、そうか。いっぱい積極的にフィーチャーされるようになってきたんですね。ということで、これからご紹介するのは、まさにこの時代。1980年代後半。結構ゴールデンエイジなんていう風に……まあ、90年代は90年代でゴールデンエイジだし、いまはいまでゴールデンエイジだから別にいいんだけど(笑)。
(高橋芳朗)アハハハハッ! ずーっとゴールデンエイジ。
(宇多丸)この素晴らしい時代を代表するラッパーというか、ヒップホップの歴史上のトップ10ラッパーとかって言ったら確実に入るんじゃないかというエリック・B&ラキムというコンビのラキムというラッパーがおりまして。このラキムさんの言葉の使い方、メタファー、非常に深い詩的な表現。あと、韻の踏み方もいままでの単純な韻の踏み方じゃなくて、ものすごい中間韻とか、頭の頭韻もちゃんとしていたりとか。格段にスキルが上がって。このラン・DMCのDMCの発言は……。
(高橋芳朗)Netflixで配信されている『ヒップホップ・エボリューション』というドキュメンタリーがあるんですけど、そこでラン・DMCのDMCが「エリック・B&ラキムが出てきた時、もう俺の時代は終わった」と……。
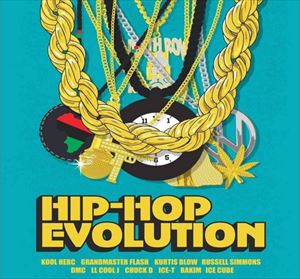
(宇多丸)ありますよねー。ねえ。そういう風に感じる瞬間ってありますよね。ということで、エリック・B&ラキムで『Paid In Full』をお聞きいただきましょう。
Eric B. & Rakim『Paid In Full』
(宇多丸)はい。エリック・B&ラキムで『Paid In Full』。1987年の曲でございます。だってさ、『Walk This Way』で1986年に全米4位のヒットを飛ばしているDMCが翌年には「俺の時代は終わった」って言ってるんですよ?
(高橋芳朗)アハハハハッ! 回転早すぎだろう?っていうね。
(宇多丸)でもそんぐらい、僕らね、すごく慌ただしく歴史を説明しているけど、そんぐらい……年刻みじゃないね。もう月刻みで進化しているのがこの時代のヒップホップですよね。もうちょっとラップの進化の話で。もう1個、ラキムはすごい詩的表現っていう感じですけども、実はこっちの方が後の売れるヒップホップには影響を与えていると思うんだけど。ストーリーテリング。要は、お話を。
(高橋芳朗)面白いお話をするっていうね。
(宇多丸)これの代表格ということでスリック・リックというラッパーがおります。後に、みなさんご存知の方もいるかな? LAのスヌープ・ドッグに非常に影響を与えたラッパーとも言われております。そもそもラキムのいまのラップの仕方、ちょっと抑えた声でやる感じとかも……オールドスクール期の「ナントカ! ナントカ! ナントカッ!」って。
(高橋芳朗)抑揚をつける感じ。
(宇多丸)(カーティス・ブロウ『The Breaks』の)「And these are the breaks!」とかと全然違う時代になっている。
(高橋芳朗)アハハハハッ!
(宇多丸)スリック・リックももうフニャフニャフニャフニャした感じで。もともとイギリスから移住しているから。
(高橋芳朗)移住してきて。で、ダグ・E・フレッシュというヒューマンビートボックスが上手い人と組んで、『La Di Da Di』っていう曲を。
(宇多丸)有名な曲がありますけども。で、まあスリック・リックのストーリーテラーとしての技術が堪能できる曲ということで。これはヨシくんチョイスですか?
(高橋芳朗)はい。じゃあ、行ってみましょうか。スリック・リックで『Children’s Story』です。
Slick Rick『Children’s Story』
(宇多丸)すいませんね。途中で。これ、スリック・リックさんがずーっとサビもなく切れ目なくひとつのストーリーを語っている曲で。最後にポンとオチがついて終わるっていうのでね。
(高橋芳朗)「Good Night」って。
(宇多丸)『Children’s Story』。これは1989年の作品です。ということで、ラップ技術の向上という話をしましたけど、それとともに歌う内容の進化もあったということですね。最近だと「Black Lives Matter」っていう運動、動きがありますけども。それの先駆けというか。

(宇多丸)きっと、ラップというとさっきから言っている「黒人が怒れるメッセージを乗せる」っていうのは実はこの時代のイメージが強いんじゃないかという風に思うんですけども。その代表的な、要するに意識が高い感じのラップをやるということで、代表的な存在としてKRS・ワンというラッパーが率いるブギー・ダウン・プロダクションズという。これはまさにサウス・ブロンクスのど真ん中から登場した、しかも先ほどから言っている、最初にヒップホップを始めた第一世代にもうケンカを売りまくって名前を売ってきたという(笑)。
(高橋芳朗)アハハハハッ!
(宇多丸)あと、たとえば先ほど渡辺志保さんの説明にもありましたが、クイーンズ地区のMCシャン『The Bridge』という曲に噛み付いて、『The Bridge Is Over』。「ブリッジ(=クイーンズ)なんて終わっている!」っていう曲を作ったというね。
(高橋芳朗)「サウス・ブロンクスからヒップホップは生まれたんだ!」っていう。
(宇多丸)そうそう。ふざけんじゃねえよ!っていうような感じの、非常に力のあるラッパーですよね。KRS・ワンでございます。自らを「ティーチャー」と呼び、ヒップホップを人種差別的なアメリカの構造を根本から変えるツールという信念に基いて活動するという。
(高橋芳朗)ラップで人を啓蒙しようみたいな、そういう感じの人ですね。
(宇多丸)という動きが出てきました。ということで、じゃあブギー・ダウン・プロダクションズより1曲、お聞きいただいましょう。1988年。これはセカンド・アルバムからの曲です。『My Philosophy』。
Boogie Down Productions『My Philosophy』
(宇多丸)ブギー・ダウン・プロダクションズ、1988年の曲です。『My Philosophy』。これ、ビデオもめちゃめちゃかっこいい。ビデオを撮っているのがファブ・ファイブ・フレディーという、先ほどもチラッと名前が出た。ブロンディーの『Rapture』の歌詞にも出てくるし、ビデオでも。後に、『YO!MTV Raps』というね、ラップ・ヒップホップ専門の番組を始めて。これがまた世界中にヒップホップ文化が広がっていくきっかけとなった。やっぱり映像がつくとだいぶ違うというのがありますよね。
(中略)
(宇多丸)ということで、非常にラップのスキル、そしてトラックというか音楽的なバリエーション。それも高まってきましたし。非常にヒップホップ・ラップが音楽的にだんだん成熟してきたという。それを象徴するグループというか、まあいまだにある意味ヒップホップのトップグループのひとつでしょうね。パブリック・エナミーというグループがございます。
(高橋芳朗)これもデフ・ジャムから。
(宇多丸)デフ・ジャムから。やっぱりね、この時期のデフ・ジャムは台風の目でございます。あ、後ろでかかっているのはパブリック・エナミーの『Bring The Noise』という曲ですね。
(宇多丸)まずパブリック・エナミーは非常に過激なというか。当時は非常に過激とされた、プロブラックというかね。黒人の意識が高まるような……アフロセントリックとか、アフリカ回帰主義とか。非常に意識が高まった時代なんですけども。そのチャック・Dの非常に強いメッセージ。そしてボム・スクワッドというトラックを作っている人たち。いままでサンプリングを使って、要するに昔のレコードをループして。繰り返し繰り返ししてやる音作りの中で、さらに複数のレコードを重ねたり。
(高橋芳朗)もうサウンドコラージュみたいな。
(宇多丸)コラージュですよね。ものすごい複雑なサウンドの作り方。ある意味、サンプリングによる音作りっていうのはいったんボム・スクワッドで行くところまで行っちゃった感。88年とか89年とかそのぐらいでね。
(DJ YANATAKE)あと、いまだとサンプリングのクリアランス(使用許諾)料がどうの
……っていうので、現代だと再現できないサウンドで。
(宇多丸)「何曲入っているんだ?」っていう。しかも、1曲あたりもジェームス・ブラウンの曲とかで、まあ使用料が高かったりしてね。大変なことに。だから、これはこの時代ならではのサウンドということで。では、パブリック・エナミーを1曲。これはね、後ろでかかっている『Bring The Noise』がいいとかいろいろとありますよ。『Rebel Without A Pause』がいいとか。どうします?
(高橋芳朗)フフフ(笑)。リクエストが来ているんで。
(宇多丸)ああ、そうです。忘れてました。リクエストをいただいております。(メールを読む)「宇多さん、長時間がんばって」ということで。ありがとうございます。じゃあ、リクエストをいただいているんで、パブリック・エナミーの代表曲といえば、これでしょう。最近でも『アトミック・ブロンド』という映画。まさに89年のベルリンが舞台の映画で鳴り響いていたりしましたね。もともとはスパイク・リーの映画『ドゥ・ザ・ライト・シング』のテーマ曲として作られた曲です。パブリック・エナミーで『Fight The Power』!
Public Enemy『Fight The Power』
(宇多丸)はい、パブリック・エナミー、1989年の『Fight The Power』をお聞きいただきました。3番でね、「エルビスは多くの人にとってヒーローだけど、俺にとっちゃあタダの人種差別のクソだ」って。「ジョン・ウェインもそうだぜ!」ってね。こういうことを歌っちゃうか?っていうのも衝撃でしたし。「俺のヒーローの大半は切手になっていない」とかね。いま聞いてもしびれるパンチラインの数々。
Public?Enemy ? Fight the Power @PublicEnemyFTP https://t.co/w3aRnlMHxY
パブリック・エナミー『Fight The Power』歌詞— みやーんZZ (@miyearnzz) 2018年1月22日
(DJ YANATAKE)これね、スパイク・リー監督の映画『ドゥ・ザ・ライト・シング』の主題歌になっているんで、映画で見ても「おおっ!」って迫力のある使われ方をしていて。
(宇多丸)だってヤナさんは当時、まだ……。
(DJ YANATAKE)そうなんですよ。高校1年生の時にたまたまアメリカに行く機会がありまして。その時にリアルタイムで……日本で公開する1年前にアメリカでわけもわからず見ていたんですけど。
(宇多丸)すごい熱気でしょう?
(DJ YANATAKE)黒人だらけの映画館でもうみんな大爆笑したり、ウオーッ!って騒ぎながら見ていたのをいまだに覚えています。
(宇多丸)ねえ。僕らも日本で公開された時に、もうライムスターを組んでいたんで。終わった後に真面目に議論したりですね。そういう時代でもありますよね。
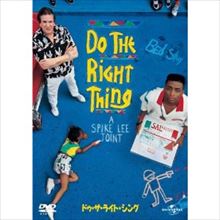
(DJ YANATAKE)はい(笑)。
(宇多丸)といったあたりで、時代は80年代末までやってまいりました。さあ、その頃日本ではいったいどのようにラップ・ヒップホップが盛り上がってきたのでしょうか?
<書き起こしおわり>
https://miyearnzzlabo.com/archives/46786
