作家のLilyさんが『THE GRANDMASTER SHOW』の『BOSS TALK』に出演。ZEEBRAさんとともに『フリースタイルダンジョン』などについて話していました。
(ZEEBRA)ということで本日の『BOSS TALK』はですね、女性3人目のゲストとなります。『フリースタイルダンジョン』ではセクシーな審査員として最近有名な作家のLilyさんです。
(Lily)よろしくお願いします。
(ZEEBRA)よろしくお願いします。もう、ダンジョンが始まってみんなはなんか、「Lilyが今日、どんなセクシーな格好をしてくるのか?」っていうのが若い子たちの噂らしいですね。
(Lily)2回ぐらいエゴサしたら、高校生ぐらいの男の子が「最初、なんだこのクソババアって思ったけど、だんだんかわいく見えた俺はもう、これでヘッズかもしれない」みたいな(笑)。
(ZEEBRA)(笑)
(Lily)うれしいのか、うれしくないのか、よくわかんない基準(笑)。まあ、ありがたいなと(笑)。
(ZEEBRA)いえいえいえ。なんかね、無理なお仕事にお付き合いさせちゃって。ダンジョンは。
(Lily)楽しくてヤバいです。本当に。
(ZEEBRA)よかった、よかった。
(Lily)ただ、やっぱり審査員なので。私、MCバトルすごい好きで。COMA-CHIさんが戦っていた両国(B BOY PARK)とか、あと結構熱い戦いになって般若さんがブチ切れた大会とかもいたりしてたので。審査員とかになると、やっぱり道端で殴られたりとか、そういうこともあるのかな?って若干覚悟を決めて挑んだんですけど(笑)。
(ZEEBRA)まあ、ヒップホップだからね(笑)。
(Lily)そうそうそう。
(ZEEBRA)ストリートのやつにね、いきなり拉致られたりとかね。
覚悟を決めて審査員に挑む
(Lily)そうなんです。と、思っていたんだけど、すごいバトルをこんな収録で見れるっていうのは、育児中の私にとってはなんかご褒美のような仕事で。そのリスクを負ってでも見たい!って。
(ZEEBRA)うんうんうん。いやいや、まあテレビを見ている人たちは、パッと脈絡がわからなかったり。Lilyがなんで審査員席にいるのかな? とか。そういうのがわからない人もいたりするかなと思うので、ここで改めて。まあ、いちばんの関係性としては、うちの奥さんと超仲がいいっていう。
(Lily)超仲いい(笑)。
(ZEEBRA)っていうのがまず1個、大前提で。だからそれでよく、ちょこちょこいろんなところでお会いしたりするんですけど。まあ、それこそMC RYUがやっていたJ-WAVEの『SOULTRAIN』。アシスタントっていう形だったんだっけ?
(Lily)そうなんです。そこに行くまで、結構私、ヒップホップの下積みが長くて。何気に(笑)。
(ZEEBRA)(笑)
(Lily)「作家になりたい」ってちっちゃい時から思っていたんですけど。まあ、文学賞とか短編小説を書いて勢い良く応募しても、かすりもしなくて。やっぱりこの夢とリアリティーの狭間でどうやっていこうかな?って思った時に、まあヒップホップはすごい高校時代とかも留学していたので好きだったのと、あと英語がしゃべれてラジオDJとして有名になった時に「本も出さないか」みたいな感じで本も出していこうかなっていう計画を立てたんですよね。19ぐらいの時に。
(ZEEBRA)うんうんうん。
(Lily)で、RYUさんが専門学校で講演会みたいなのがあるって言ったので、大学生だったんで行って。「アシスタントになりたいです」って言ってから、私のすごい結構ハードなヒップホップの下積みが始まって(笑)。で、クラブで。ラジオでしゃべりたかったんですけど、なかなか番組とかも持たせてもらえないので。まあ、「現場だ!」みたいな感じで言われたので。クラブも好きだったので、DJのサイドMCとして結構がんばり、なんかフライヤーに小さく名前を入れてもらうのに……
(ZEEBRA)(笑)。それって、何年ごろ?
辛いヒップホップ下積み時代
(Lily)私が19とかだから、2001年とかです。2001年から。私、いま本とか出せるようになってから思うのは、ライターとして結構私トントン拍子にすぐ本を出してヒットにも恵まれて。ヒップホップのMCとしてがいちばんキツい下積みだった(笑)。
(ZEEBRA)実はね(笑)。
(Lily)実は。チケット代とかも払わないとフライヤーに名前とか載らなくて。
(ZEEBRA)ノルマがあったわけね(笑)。
(Lily)ノルマがあって。渋谷のFAMILYで初めてフライヤーに名前が載ったんですけど。
(ZEEBRA)うんうん。いや、もうFAMILYって言ったらもう下積み中の下積みですよ。まさに。なんだろうな? いまでもまあ、ちょっといい感じの好き放題やれる小箱っていうことで、それこそキングギドラのDJ OASISとかがいま、月一とかでやったりしてるけど。あれは本当、それこそUstreamでやる感じで、「ちょっと実験的に夕方とかやってみよう」みたいな感じでやる、まさに小箱(笑)。
(Lily)そこと、池袋のBEDでマイクを持って(笑)。
(ZEEBRA)ハンパない(笑)。
(Lily)で、その時に付き合っていた彼がDJだったので。その彼もお金を払いながらイベントに出ていて。だから、2人でお金も全然ないんだけど、やっぱりヒップホップの活動をするのにいちばんお金がかかっていて。バイトも私、5個ぐらいかけ持ちしていて。それこそ、ロックンローラーのお兄ちゃんが歌詞を書くのの英語を喫茶店で教えて小銭を稼いでて。それがヒップホップに流れて……みたいな(笑)。
(ZEEBRA)(笑)
(Lily)結構大変。だから本当に、ヘッズの下積みの気持ちとか、フライヤーの名前がやっぱり大御所っていうか、1回ギャラもらえるようになった人は絶対にどかないから。そこの世代交代したいのに、「まだこいつ、スペシャルゲストだよ!」みたいな。どう考えてもそこに行けない、そのフライヤーの枠の取り合いとか。なんか結構リアルに……だから本当に泣けるんですよね(笑)。
(ZEEBRA)そうだね。ダンジョン、まさにそういうのね。はじめの紹介VTRのところでいろいろ流れるもんね。
(Lily)はい。
(ZEEBRA)そうかそうか。まあ、それこそそういったバックグラウンドを全く知らない。視聴者の方々は。もちろん番組がさ、ああいう番組だからもう野郎ばっかりで、むさ苦しくて、なんだなと思って。一輪の花ということで出ていただいているんですけど。だから本当、パッと見た人は、「ああ、作家さんね。女性枠みたいな感じで入っているのかな?」って思うと思うんだけど、全然そういう風にヒップホップ、超いろいろ詳しくて。
(Lily)結構ハードですよね。ヒップホップは、でも。弟もラッパーなんですけど、まだやっぱりバイトも辞めれてなくて。で、3個下なので、もう32とかなので。やっぱり家族、親とかは心配したりとか。だから、ヒップホップに心を奪われてしまったことによって、すごく生きにくくなるっていうリアリティーとか。
(ZEEBRA)うんうんうん。
(Lily)だからうちの両親とかはZEEBRAさんの自伝とかも全部読んで研究して。家族の話し合いの時とかにお母さんが「うちはZEEBRAとは違うよの!」とかって(笑)。だから、マイノリティーの音楽ですよね。
(ZEEBRA)うんうん。
(Lily)だからそこにすごく刺さるというか。それで、男ばかりの現場って言いますけど、女性であることもマイノリティーであったりとかして。やっぱり小さい時から私は特に母に「これからは女性も社会で働く時代だから」とか。だからそこでシンパシーを感じてる部分もありますよね。
(ZEEBRA)それこそだってね、90年代とかで言ったらさ、ローリン・ヒル(Lauryn Hill)とかさ、そのへんがそれこそ、その後ビヨンセ(Beyonce)とかも言っていたけど。「Independent Woman」っていうかさ。そういう感じをバチーンと打ち出したのはまさにヒップホップだと思うし。
(Lily)本当にそうですよね。
(ZEEBRA)それまでは、なかったもんね。なんだろう? マドンナ(Madonna)とかそういうのがちょっとそういう風に強い女性っていうのはやっていたかもしれないけど、たとえば知識とかさ。そういうことまで全部ひっくるめて、内面の強い、しっかりした女性っていうもののかっこよさっていうのが結構あのぐらいの頃から。
(Lily)そうですね。ちょうどローリン・ヒルのグラミーをとった『The Miseducation of Lauryn Hill』の時に、ちょうど高校時代でフロリダに留学していたんですけど。その前から、ヒップホップってやっぱりすごくオラオラだったり、男だったり、ギャングスタだったり。そこらへんがかっこよくて聞いていた部分もあったんですけど。フロリダの普通に現地校に行っていたんですけど、クラスに1人は妊婦がいるような高校だったんですよ。
(ZEEBRA)ああー。
(Lily)それも、日本では考えられないんだけど。底抜けというか、「この人が好き!」ってなったら「付き合いたい」を飛び越えて、彼との永遠の絆がほしいから。子供を産めば永遠にベイビーママとベイビーパパって。そういうような女の子たちがいる中でローリン・ヒルのアルバムって全てを教えていたんですよね。女の子に。
(ZEEBRA)うん。
(Lily)男の人に好かれたいと思って体を見せたりとか、媚びたりとか、そうやって脱落していくから。自分を高く持つこととか。そこで私はやっぱりあのアルバムでヒップホップの女性としてというか、本当に教科書だなって思ったんですよね。で、学校の、それも日本では考えられないんですけど。社会の、ソーシャル・スタディーズの先生がローリン・ヒルの大ファンで。
(ZEEBRA)うんうん。
(Lily)それこそこういうテーブルにローリンのを飾っていて。「She is a beauty.」みたいな感じで。なんかそこまで浸透してたんですよね。
(中略)
(ZEEBRA)ダンジョンっていうかMCバトルの面白いところって、それこそDOTAMAとかさ。
(Lily)はい、もうDOTAMAさん!
(ZEEBRA)ああいうさ、普通にうちらで言ったらもうドンズバのヒップホップじゃないかもしれない、もうストリート感ゼロみたいなさ。ああいうやつらがさ、それこそさっきから話しているような、その主張の塊だったりするところだったり。そういうのがバランスよく出てくることが、たぶんいろんな層にウケてるのかなって気もするし。そろそろね、フィメールラッパーも出てきてほしいなって。
(Lily)絶対に盛り上がりますよね。やっぱ、男女のケンカってすっごい面白いじゃないですか。いちばん傷つくんですけど。それはやっぱ、男対女で。
(ZEEBRA)やったらどうなるかな?って。
(Lily)超面白いですよね。なんで男女のケンカってあんなにエンターテイメントなんだろう?って。自分がそこに出場していると本当に辛いしエグいし、本当にしんどいじゃないですか。だけど、男女はケンカし続けながらも一緒にいて。愛憎っていうか。夫婦とかもそうですし、恋人も。
(ZEEBRA)うんうん。
(Lily)ケンカって面白いですよね。あとこう、いちばんみんな言いたいのに、それを言っちゃいけないと思っていたことを誰かが言ってくれる時のなんか、あのスカッと感ったらないですよね(笑)。
(ZEEBRA)(笑)
(Lily)「言っちゃった!」みたいな(笑)。だからそういうのをいつも期待してて。みんな審査員の方も。私はラップとかできないので、見るところはニワカなところがすごいあると思うんですけど。そこを個人的にはすごい楽しみにしてるんです。「どういう悪口をこの人は言うだろう?」って。
(ZEEBRA)うんうん。
(Lily)だから悪口の的確さみたいなので、私はすごい見ちゃうのかもしれないです。みんな、たとえば小学校でも、たとえば担任の先生がいい人で。たとえばそのヅラとか絶対に気づいているのにみんな言っちゃいけないとか。それを1人が言ってくれたらスカッとするとか。なんかそういう、「よくぞ言ってくれた!」みたいな。
(ZEEBRA)うんうんうん。
(Lily)あと、悪口を言われた。それを返せる器のデカさとかもたぶん、あわせてかっこいいんですよね。
(ZEEBRA)ああ、そうだね。間違いない。間違いない。もう自分の半分ぐらいの歳の若い子にさ、もうなんだかんだ言わせながらも「ん?」ってやっている漢がかっこいいとかね。
(Lily)かっこいいですよね!
(ZEEBRA)うん、そうそうそう。たしかに本当、その通り。なんか、やっぱりダンジョンでどんどんどんどんそういう空気が一般的にもそういう感覚……もちろん、俺は「ああ、ヒップホップって、韻を踏むってこういうことなのね。ああ、この人たち、こんな高度なことを普段やっているんだ、すげー!」って思ってくれたらもちろんうれしいんだけど。それと同時に、さっきから話してたりしているような主張……「主張する日本人」みたいな感じの画がどんどん広がっていったらいいなと思うし。
(Lily)そうですね。
審査員のコンセプト
(ZEEBRA)まあ、本当にそういう意味も含めてね、ラッパーが専門的な審査だけをしていたらね、絶対に広がらないなと思ったから、はじめから5人の審査員のうち、3人はそういうMCバトルに長けた審査員がいて。で、あと2人はやっぱり何か言葉に長けた人に来てもらった方がいいだろうというところからスタートして。それで、そしたら絶対に女性も1人いた方がいいし……ああ、(いとう)せいこうさんとLilyに決まってんだろ!って俺の中でパパーン!って決まって。
(Lily)でも最初は不安じゃなかったですか? 私も最初は不安だった。行ってみたらやっぱり想像していた以上にアウェイで。私の人見知りな面がすっごい出てたんだけど。
(ZEEBRA)(笑)。いや、いちばんはじめの1回、2回は大変だろうなって俺も思ったし。もちろん、俺もほら、「フリースタイルダンジョン」でエゴサして。で、「なに言ってる、かに言ってる」ってすっげーチェックしてたから。「あ、Lily結構大変そう……」って思った(笑)。いちばんはじめ。
(Lily)私、超ディスられると思ってたんだよ。めっちゃディスられてるなと思って。
(ZEEBRA)いや、でもあれは本当に、審査員制度っていうのがね、1回崩壊したんだよ。昔。『B BOY PARK』のMCバトルは審査員制度だったんだけど、それが完全に……それこそ般若だったり、漢だったりが台頭してきた時代で完全に崩壊して。もうみんな、審査員に楯突くみたいなのが始まっちゃって(笑)。

(Lily)その時にいたからガクブルだったんですよね(笑)。
(ZEEBRA)でもね、あの当時の審査員は、もう全員が全員、MCバトルもクソもわからない人たち。というか、実際にMCバトルを自分たちもやったことがないし。MCバトル自体を日本でもそろそろできんじゃねえか?っていう時代に言い出して。『B BOY PARK』でやってみましょうかって、まずやってみたぐらいの頃だったから。あれがまあ、1年、2年、3年。で、KREVAが連勝して……とかっていうのがあって。もう本当、審査員もやっている側も手探りでやっていた頃だったから。もうディスられてもしょうがないっていえば、しょうがないんだよね。
(Lily)そうですよね。
(ZEEBRA)で、当時俺らもちょっと考え方がまだ浅はかだったなと思うのは、たとえば向こうのMCバトルとかDJバトルとか。ニューミュージックセミナーのMCバトル、DJバトルをみんな見ると、たとえばMCバトルなのにDJのすごい、たとえばDJプレミア(DJ Premier)が審査員にいたりとか何とかってやっているかもしれないけど。それはやっぱり、DJたちももっとその当時のDJたちよりラップとは何か? をわかっていた。やっぱり。っていうのは、日本語ラップとは何か?っていうこと自体がまだまだこれから成長していく中で、DJたちもそこまでラップの細かい詳しいこと。いま、それこそKEN THE 390とかERONEとかが言うような、すごく細かいことまでは説明できるような立場じゃなかったし、わからなかったと思う。
(Lily)みなさん、本当に上手ですよね。私も聞きながら、「おおーっ!」って思いますもん。
(ZEEBRA)そうそうそう。でもたぶんあれは、ああいう風に実際あいつらもMCバトルに出ていて。自分たちで「こうやって、こうやって……」っていうのも研究しながらやってきた人たちだから理解していて。で、そういう人たちが増えたからこそ、審査員制度がもう1回、復活できたんだと。で、それは俺も『高校生ラップ選手権』の時に、俺は「審査員制度を使おう」っつって。
(Lily)うん。
(ZEEBRA)っていうのは、どうしてもやっぱり、もちろんお客さんに審査させるっていうのもひとつ、すごくいいとは思うんだけど。ちょっとそれに寄りすぎちゃった時代があったかもなって、俺は見ていて正直思ったから。高校生ラップからは1回、それをやろうよと。んで、「ちゃんと本当に上手いやつらに来てもらえば審査もしっかりできるはずだし」っつって。で、R-指定とかにそのへんを呼んだらみんなバッチリだったから。っていうので復活したやり方なのね。だから、そういったものすごいテクニカルな話とかが聞きたいっていうのがパッと普通に思うことかもしれないんだけど。
(Lily)うん。
(ZEEBRA)ただ、それだけだと絶対に裾野が広がらなくて。やっぱりそれを一般的な感覚で見た時とかに、どういう風にそれを言えるか? で、やっぱりせいこうさんとLilyの言うことっていうのは、俺はもう、普段審査員に「どうですか? こうですか?」って振る時、なんとなくバランスなんだけど。やっぱりテクニカルな話をしてもらうのと、もう少しオールオーバーな話をしてもらうのとっていうので。そのバランスはすっごい大切なんだと。それがだんだんわかってきたじゃん。お客さんも。
(Lily)そうですね。うん。
(ZEEBRA)だからもういまは、むしろ「おっ、今回のLily、谷間がバッチリ!」とかさ(笑)。
(Lily)そっち?(笑)。コメントを褒めてくれるのかと、すっごいいま……(笑)。
(ZEEBRA)いやいやいや(笑)。むしろそういう風に楽しんでもらえるようになったというか。もう全部ひっくるめてバランス。だから、たとえば女子だからこそ、こういう風なことに目をつけるんだとか。それってすごく、女子はたぶん見ている人たちはたぶん「そうなのよ、そうなのよ!」って思うと思うし。どんどん、たとえば男子もみんなリリックの中とかでもさ、「じゃあ次はLilyさん、俺に上げてくれ」とかさ、言ってきたりするじゃん?
(Lily)ああ、言ってましたね(笑)。
(ZEEBRA)あれ、他のやつは誰も言わないからね。なんかそういう意味では、全部の中のすごくエッセンスになっているし。もう非常に、ありがとうございますっていう。
(Lily)本当に、こちらこそですよ。この青と赤(のボタン)を押す時に、私はライターとか作家とかでデビューしていく時よりも、本当にヒップホップの下積みが結構大変だったんですよね。その、DJブースのところで、「Put your hands in the air!」みたいなことを叫んでいる役だったんだけど。「If you are the motherfucker, bounce bounce bounce!」とかいろいろ言っていたら、「てめー、マザーファッカーって俺のこと言っただろ?」みたいな人に絡まれて、ツバをかけられて超ケンカになったりとか。
(ZEEBRA)ハンパないね(笑)。
(Lily)結構ヒップホップの下積みはすっごい辛かったので。そこのバトルに出ていた審査員だったらバトルのことを……私は下積みヒップホップ、マジでヤバかったなっていうトラウマみたいなのがあるから。それをバイトしながらずーっとやって。それでもヒップホップに魂を奪われて。その人たちにとって、『フリースタイルダンジョン』に出るっていうのはすっごいチャンスなわけじゃないですか。地上波で、こんなにバズッてて。
(ZEEBRA)はいはい。
(Lily)そこで勝つか負けるかっていうのが、5人しかいない審査員で。普段、ヒップホップ漬けだったこともあるけど、いつも育児とかをしている私のこれに、もう人生がかかっているんですよ。それを思うと本当に指が震えるし。だから本当に収録の後は倒れるようになるぐらい、「知識がない分、一語一句絶対にもらさずに聞いて、全部メモろう! リリック帳に」みたいな感じで。
(ZEEBRA)うんうん。
(Lily)そういう意味ではすっごい、魂を削って審査させていただいているみたいな(笑)。
(ZEEBRA)いや、間違いない(笑)。本当ね、俺もだから高校生ラップの審査員をやっていたから、その気持ちはすっごいよくわかるし。ただもう、俺は少しこれに関してはね、ダンジョンはやっぱりひとつポイントなのはゲームなんだと。そこを俺はすごく意識していて。みんなにもそういう風に思ってもらいたくて。っていうのは、やっぱり本当にガチで戦ったら、チャレンジャーが毎回先攻後攻を選べるとか、違うと思うんだよね。
(Lily)ああ、そうですね。
(ZEEBRA)だから、いろんな意味で。たとえばじゃあモンスターは毎週テレビに出てくるモンスターたち。先週なにをやっていた、かにをやっていたをテレビとかで見られていて。それがあんだけの視聴者みんなに見られているそのど真ん中で、「お前、先週○○とやった時にこうだったじゃねえか!」って言われたら、それはもう格好のネタになっちゃったりする。
(Lily)そうですよね。
(ZEEBRA)だからそういう意味でもう、全然イーブンじゃないわけよ。だからそん中で、もう本当に時の運もあると思うし、ビートの運もあると思うし。組み合わせの運もあると思うし。だからもう、本当にそのゲームだから。本当にその瞬間だからっていう風に考えて。だからほら、たまに「えっ、これでクリティカル?」っていう時もあるじゃん。
(Lily)うんうん。
(ZEEBRA)もうみんな、ギリギリのところで「うーん、まあ……青だ」って思って押したら、みんな青を青していたとか。みんな赤を押していたっていうのはあるから。でも、あれはあえて「もう1回」っていうのがないっていうのがこのルールでもあったりするから。
(Lily)だから緊張するは緊張するんですけど。そのシビアさがまたすごくいいんですよね。あと、そこでダメでもまたリベンジシステムもすごく好きで。そこでじゃあ、リベンジに呼んでもらえる人と呼んでもらえない人の差とか、そこもだから、人生は不公平何ですよね。そこでちょっとカリスマ性があって、もう1回見たいとか、それこそ現場の声じゃないけど「あの人を見たい」とか。そこは、もうフェアじゃないっていうのはアーティストを目指している時点でフェアなわけないんですよ。あえて、そこの土俵に行っているわけで。
(ZEEBRA)そうだね。うんうん。
(Lily)だからそこの、夢追い人はみんな泣けるっていうか。だから経営者の人とかも『フリースタイルダンジョン』、見てるし。言葉が好きな吉本ばななさんとかもそうでしたし。

(ZEEBRA)うんうん。
(Lily)いろんなところに刺さる要素がすごくいっぱいあるんだろうなって。フェアじゃないんですよ。
(ZEEBRA)そうなんですよね。
(Lily)マイノリティーだから、余計なんか反骨精神みたいな。そのスピリットが大好きですね。
(中略)
(ZEEBRA)メインのお話もちょっとしたかったんですよ。作家さんとしての。
(Lily)あ、はいはい。そっか(笑)。
本と歌詞の違い
(ZEEBRA)で、俺はそれこそ前に知り合ったぐらいの頃だったのかな? もうちょっと前だったのかな? (Mummy-)DがフィーチャリングでSoweluの曲の歌詞を書いたってあったじゃないですか。あのへんって、歌詞を書くっていうのと本を書くのの違いを俺、すごく聞いてみたかったんだけど。
(Lily)全然違うんですよね。歌詞の方が難しいですよね。
(ZEEBRA)ああ、本当?
(Lily)そのSoweluとDさんの時はちょうど私が『こぼれそうな唇』っていう小説を書いてリリースする時で。Soweluの曲を結構、アルバムのを何曲も何曲も作詞を一緒にしたりとか、私が書いたりしていた中で、Dさんと……2人ともDさんにはメロメロな感じで。「エロい曲がいいね」みたいな感じで。その時は私、産後で赤ちゃんを連れて打ち合わせに行ったんですけど。「カーセックスの曲をお願いします」ってDさんにお願いして、Dさん「ええっ!?」みたいになったんですけど。
(ZEEBRA)(笑)
(Lily)そこで、やっぱりセックスシーンとかも小説だと、本当に自分の好みじゃないですけど、尺がないから。やっぱりすごく作り込めるんですね。で、じゃあ曲にしようってなった時に、やっぱりメロディーもあるし。
(ZEEBRA)そう。言葉数ね。
(Lily)言葉数。あと、別にラップじゃなくても語呂とか韻とかはやっぱりすごく大事になってくるし。最近、改めて思いました。(青山)テルマの曲を一緒に書かせてもらったんですけど。その時も、「ああ、やっぱり私は長文の方が向いているのかもな」って思うぐらい歌詞はやっぱり違いますね。
(ZEEBRA)そうだよね。むしろだから俺は歌詞を書く方がメインだから。本を書くってまた全然違うよなって思って。
(Lily)うんうん。
(ZEEBRA)なんか俺、前に自伝を出した時って、あれは実は書いてくれているライターさんがいて。俺がしゃべって。
(Lily)語りおろしで。
(ZEEBRA)そうそう。そういう感じでやっているんだけど。まあ、自分で書いた方が面白いかもなって思って。たまーに書いてみて、それをどんどん、トピックごとにいろんなのを書いて。それがたまったら本にしようかなって思って、たまに書いてるんだけど……すっげー大変。
(Lily)大変ですよね。執筆は本当に大変。
(ZEEBRA)なんかね……俺は逆にこうなってないから。言葉数が決まったりしていない分、脈絡がないっていうか。
(Lily)膨大にある(笑)。
(ZEEBRA)そう。話がボンボン飛んでっちゃうし、話をまとめてキュッとここのポイントで書きたいんだけど、このことを説明するにはこのことも説明しなきゃいけないし、このことも説明しなきゃいけないうちに……このことを説明する途中の説明をしている時に、これを説明するためにはこの裏側のここをわかってもらわないと……ってやっていると、だんだん言いたいことが逸れていっちゃうっていうか、散漫になっていっちゃって。すげー難しいなと思って。
(Lily)たぶんそれもMCバトルとか歌詞を書くコツと一緒で、たぶん構成がひとつ自分のあれがあるんでしょうね。無意識のうちに。だから、チャプター分けとか。だいたい章立てとキャプターのキャッチコピーみたいなのができると、だいたいエッセイとかは流れていくんですよね。
(ZEEBRA)あ、目次から作っていく感じ?
(Lily)そうです、そうです。しかも目次のチャプターのところにパンチラインを置くんですよ。そうすると、自分がそのパンチラインに響いていればブレないんですよね。
(ZEEBRA)ああー、K DUB SHINEみたいな感じだ。
(Lily)(笑)
(ZEEBRA)キングギドラのね、アルバムの作り方に近いかな。キングギドラのアルバムは、だいたい毎回こっちゃんがテーマとか、なんとなくタイトルとかみたいなのを出してきて。で、「はあはあ、いいじゃない、いいじゃない」っつって。で、こういうバーッと出た中で、「じゃあこういう風なのもあってもいいかもね」みたいなのも1、2曲、俺が言うか言わないかぐらいで。だいたいメインのコンセプトはこっちゃんが決めてくるんだけど。そこでたとえば、曲タイとかパッとあったりすると、「ああーっ」って。ババババッと自分の中にイメージが広がるわけ。
(Lily)そうですか。曲順とかと似ているかもです。
(ZEEBRA)そうそう。
(Lily)最後はじゃあ、このメロウなので締めようとか。でも、自分が書いた方が面白いのは絶対にそうです。
(ZEEBRA)そういうことだよね。じゃあ、わかった。俺も曲タイから。こっちゃんスタイルで。
(Lily)あ、ヤバい。楽しみです。超楽しみです。あと、ZEEBRAさんの「一点突破」っていう『Mr. Dynamite』をたぶん日本でいちばんカラオケで歌っている女性だと思うんですよ。
(ZEEBRA)(笑)
(Lily)たぶん1000回は絶対に歌っているぐらい。私、まず1曲目に『Mr. Dynamite』を絶対に入れる、みたいな(笑)。
(ZEEBRA)それこそあのビートとか、俺、自分で作っているんだけど。あれとかはまだまだチキチキ(ビート)とかって、「チキチキ嫌い」とか言っているやつらがいた頃に、ちょっとああいうビート感出。
(Lily)もう最高で。あまりにも好きすぎて『一点突破』っていう短編を小説で書いたぐらい好きです。ぜひ、B-BOYに読んでほしくって。
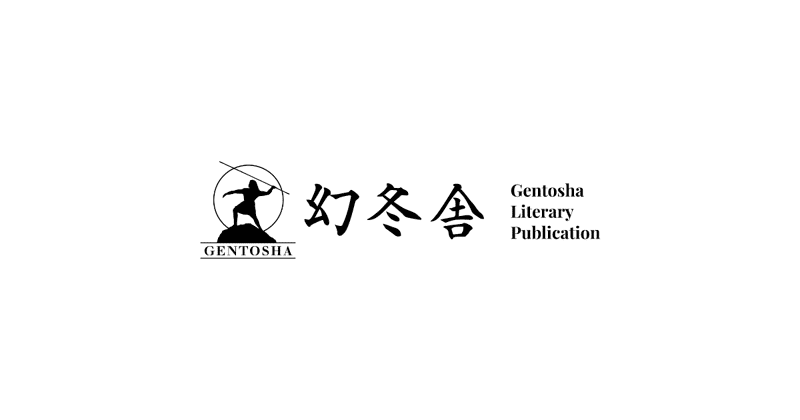
(ZEEBRA)うんうん。そうだね。基本、普段女の子のファンがすごい多いっていう印象があるし。
(Lily)99.9%。むしろ男性には嫌われるような本を書いているから。
(ZEEBRA)あ、そう?(笑)。
(Lily)だからそのダンジョンで「クソババア」っていうレスポンスは正しくて。そうなんですよ。私、男の人がムカつくようなことを、だからMCバトルじゃないけど、それを代弁することで、女性に人気みたいな感じのあれなんで(笑)。
(ZEEBRA)(笑)。まあでもね、むしろ男性もさ、「これは言ったら女性に引かれるわ」みたいなことを言う男性っていうのも、またそれはそれで男性に「ウワーッ!」ってなるし。それは必要な存在だし。
(Lily)やっぱり、分かれますよね。両方に人気って無理なんですよ。男の中の男だっていう人、だいたい私、嫌いですもん。
(ZEEBRA)ああー。
(Lily)「うわっ、ムカつく!」って。だからまた、男に人気なんですよね。女から嫌われているところがまた熱い! みたいな。
(ZEEBRA)うんうん。なるほどね。
(Lily)でも、たぶんZEEBRAさんもそうかもですけど、そういうなんか、『おとこのつうしんぼ』っていうので、「こういう男は許せない」とか、「男の浮気を許すなんて、アリじゃない? 逆に」とか。そういう強いことを20代の頃にガンガン、オラオラで書いていたんですけど。どんどん優しくなってきちゃって。
(ZEEBRA)(笑)
(Lily)なんか自分もすっごい優しくなってきちゃって。良くも悪くも。
(ZEEBRA)だんだん許容がね。うん。まあそれは、また別な面じゃないですかね。男性女性とかっていうことよりも、人間の成長とか、そういうことだったりするのかなって気もするし。
(Lily)そうですね。だからはじめてZEEBRAさんと飲んだ時。みんなで、なんかダブルデートみたいにしたじゃないですか。その時にヒップホップと新生児のかわいさについて2人で話していて。
(ZEEBRA)(笑)
(Lily)お互いになんか、連れは寝ているみたいな感じで(笑)。「新生児、ヤバくない? 首がヤバくない?」みたいな(笑)。
(ZEEBRA)「関節、もう1個あるよ」みたいな(笑)。
(Lily)そうそうそう(笑)。そういう感じになってきますよね。
(ZEEBRA)だから、もう本当にみんなそれぞれ。もうヒップホップなんかさ、どんなこともトピックにするし。ヒップホップ=ライフみたいな部分があるから。新生児の話をするのも、俺にとってはヒップホップだし。
ヒップホップ=ライフ
(Lily)本当、そうですよね。ZORNさんの「洗濯物干すのもヒップホップ」って私、いっつも毎日考えています。
(ZEEBRA)うん。
(Lily)「(子供の)送り迎えもヒップホップ」って思ってやってますし(笑)。
(ZEEBRA)あの、なんだろう。たとえば「なにがヒップホップだよ?」っていう人たちに言うとしたら、「1個、考えています」っていうことかな。俺だったら、洗濯物を干すとしたら、「これをこっちからこういう順番にしていった方が乾くかな?」とか考えるのがヒップホップ。
(Lily)いや、生活の土臭さがヒップホップ。なんか送り迎えとかも結構すごい大変だし。スッピンで送り迎え。いっつも時間に追われてお母さん業をやっていて。お母さんたちにはヒップホップって私、刺さるなって思うのも、生きるのが大変なのがヒップホップなんですよね。
(ZEEBRA)ああー。
(Lily)汗水たらして、だけど前を向く。すっごい辛いこととか数えきれないけど、だけど明るく行く。なんかニューオーリンズに旅をした友達が言っていたんですけど。奴隷制度があったところって、ジャズとかフォークとか、陽気な、それこそサウスも「なんでこんなバカなんだろう?」ぐらいの。ヒップホップもそうだけど。人生が過酷だから、振り切るんですって。ハッピーに。
(ZEEBRA)うんうんうん。
(Lily)だから、そこも私、すっごいヒップホップだなと思っていて。だからポジティブなんですよね。どんなに辛くても、笑っていく。前を向く。そこにすごくやられます。
(ZEEBRA)うん。間違いない。もう、そうだね。俺なんか、だからそれこそ「スニーカーを磨くのもヒップホップ」じゃない?
(Lily)ああ、ヒップホップですよ。
(ZEEBRA)よくさ、まあストレートにヒップホップかどうかわからないけど。向こうでさ、すっごいサグなやつがさ、タンクトップ1枚でさ、ドゥーラグみたいな巻いてさ。シャツにアイロンかけてんの。
(Lily)ああ、超ヒップホップ!
(ZEEBRA)超かっこいいじゃん?
(Lily)だから、ヒップでいたいってことなんですよね。お金がなくても、俺のスニーカーはピカピカ、みたいな。
(ZEEBRA)そうそうそう。だからまあ、そういった部分までひっくるめて、土臭いところまでひっくるめて。やっぱり、でもかっこよさを求める、みたいなことなのかな?
(Lily)本当にそうですね。過酷だし、金はないけど俺のチェーン、みたいな。その買うのを無理してんのもヒップホップだし(笑)。
(ZEEBRA)そうだね。武士は食わねど高楊枝みたいなね。
(Lily)そうそう。だから、『VOGUE』の編集者とかが結構ギャングスタラップ好きな人がいて。なんだろう?って思ったら、それも似ているんですよ。私、お腹空いてお金がなくてもバラを買います。それはカッコつけているわけじゃなくて、うっとりすることの方が生きやすいから。お腹空いていても、バラが部屋に飾ってあって。「ああ、素敵」って思うと、辛いことを忘れられるっていうのと、たぶんB-BOYのスニーカーをピカピカにするのは似ていて。
(ZEEBRA)うんうん。
(Lily)だから『VOGUE』も無理している見栄じゃないですか。って思うと、世の中の全てがヒップホップなんですよね(笑)。
(ZEEBRA)(笑)。たしかにね。そういうことですな。では、告知の方を。
(Lily)これ(『青春、残り5分です。』)は漫画なんですけど。それこそヒップホップに通じる、「夢を追う」っていう大変さ。専門学校で自分はなにをやりたいか。スタイリストを目指してもがく。かっこつけたい、お金ない、だけど夢をつかみたい、みたいな漫画がいま、『NYLON』で原作をやっているんですけど。その2巻が5月28日に出ます。1巻は発売中なんで、ぜひ読んでください。
(ZEEBRA)ぜひチェックしてください。あのね、『フリースタイルダンジョン』のオリジナル・サウンドトラック。コンピみたいなのがリリースされるんだけど。残念ながら、Lilyだけはどうやって参加してもらおうか、本当に悩んだ結果が……(笑)。
(Lily)(笑)
(ZEEBRA)ジャケでセクシーポーズをしてもらおうか? とか、いろいろ話が出たんだけど(笑)。
(Lily)マジで売れなくなる(笑)。
(ZEEBRA)ちょっと今回はそのサントラの裏テイクみたいな感じで、いろいろ話ができたかなって。
(Lily)めっちゃ気を使っていただいて、ありがとうございます(笑)。
(ZEEBRA)いえいえいえ。まあ今後もヒリヒリな審査をしていただくことになると思うんですが。お付き合いをお願いします。
(Lily)こちらこそ、よろしくお願いします。
(ZEEBRA)ということで、今回のゲストはLilyさんでした。ありがとうございました。
(Lily)ありがとうございました。楽しかったです(笑)。
<書き起こしおわり>
